
2025.10.14
ゴミ屋敷の原因にもなる「ためこみ症」の特徴と改善策
物を過剰にため込む状態が続くと、家の中や玄関周りが大量の物であふれ、「ゴミ屋敷」と呼ばれる状況につながることがあります。ためこみ症の改善には、無理に捨てさせる・片付けさせるのではなく、本人の気持ちや状況に寄り添いながら、少しずつ生活を整えていくことが大切です。
この記事では、ためこみ症の特徴や日常生活への影響、改善につながるサポートについてご紹介します。
ためこみ症の特徴
ためこみ症とは、使わない物であっても捨てることに強い抵抗を感じ、多くの物をため込んでしまう傾向をいいます。医学的には「ホーディング(Hoarding)」とも呼ばれ、「他の人にとってほとんど価値がないと思われるモノを大量にため込み、処分できない行為」 と定義されています。
一般的に見られる特徴としては、以下のような傾向があります。
• 物を手放すことに強い苦痛を感じ、どうしても捨てることができない
• 家族や他人が物を片付けることに強く反発する
• 実際にはほとんど価値のない物であっても、自分にとっては「まだ使える物」「いつか使える物」であり、処分する理由がないと感じている
• 部屋の中はため込んだ物であふれており、日常生活に支障をきたしている
ためこみ症の背景には、遺伝的要因や過去の喪失体験、幼少期の生活環境などがあり、さまざまな要因が関連しているといわれています。一人ひとり状況や背景は異なるため、無理に変えようとするのではなく、ゆっくりと向き合っていくことが大切です。
ためこみ症が日常生活に与える影響
ためこみ症は、ただ「物が多い」という状態だけでなく、日常生活にさまざまな影響をもたらす可能性があります。
ゴミ屋敷化
ためこみ症の状態が続くと、家の中に物があふれ、いわゆる「ゴミ屋敷」と呼ばれる状態に近づいていきます。家に物が散乱しているような状態では生活動線が確保できなくなり、食事・入浴・睡眠といった基本的な日常生活にも支障をきたしかねません。また、室内に収まりきらなくなった物が玄関や共有スペースにまで置かれるようになると、異臭や害虫の発生、火災のリスクが高まり、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあります。
心身の健康問題
衛生的な居住空間を保つことは、生活の質を確保ための重要な要素の一つです。足の踏み場もないほど物があふれ返っている環境では、生活の質が低下し、心理的なストレスが増加してしまいます。また、物が大量にあることで掃除が行き届かなくなると、ほこりやカビの発生など衛生環境にも影響が生じ、本人や家族の健康被害につながる可能性があります。
周囲からの孤立
周囲からは「ゴミ」と見なされるような物であっても、本人にとっては手放したくない持ち物であるため、この価値観の違いが家族や知人との間で誤解や衝突を生むことも少なくありません。また、「早く片付けたほうがいい」「これは捨てるべきだ」といった周囲からの助言や指摘が、本人には責められているように感じられ、心を閉ざしてしまうこともあります。
ためこみ症を改善する方法
ためこみ症を改善するには、一人ひとりの状況に合わせたアプローチが欠かせません。気持ちや背景に寄り添いながら、専門的な支援や周囲の協力を取り入れることが求められます。
認知行動療法
ためこみ症の改善には、認知行動療法(CBT)が有効とされています。物をため込む思考や行動に目を向ける心理的な支援方法であり、例えば「いつか使うかもしれないから捨てたくない」といった思考に働きかけ、それが本当に必要な物なのかどうかを適切に判断できるように支援します。すぐに効果が現れるものではありませんが、専門家と連携しながら段階的に進めていくことが大切です。
環境調整
居住空間に足の踏み場がなく、ゴミ屋敷に近い状態になっている場合には、家族や専門家が介入して環境の整理を手伝う方法もあります。また、片付けに特化した民間業者を利用するなど、外部の手を借りながら物理的なスペースを確保するのも一つの方法です。
ただし、ためこみ症の本人は「捨てること」「片付けること」に苦痛を感じており、無理に進めるとかえって不安や反発を強めてしまうおそれがあります。専門家とも連携しながら話し合いを重ね、少しずつ改善を目指していくことが大切です。
家族の理解と協力
ためこみ症の改善には、家族や身近な人の理解と協力が欠かせません。無理に片づけを促すのではなく、本人の気持ちに寄り添いながら関わることが求められます。しかし、家族としてもどのように接すればよいかわからず、不安や戸惑い、精神的な負担を感じることがあるかもしれません。家族自身も一人で抱え込まず、医療機関やカウンセラーなどの専門家によるサポートを受けながら、無理のない関わり方を見つけていくのが望ましいでしょう。
まとめ
ためこみ症は、物を手放すことに強い苦痛を感じ、価値のない物でもため込んでしまう傾向のことです。今すぐの改善は難しくても、専門家の支援を受けたり、家族の理解・協力を得ながら取り組むことで、少しずつ前向きな変化が生まれてくることが期待できます。
遺品整理・生前整理の「ワンズライフ」は、遺品整理士認定協会より優良事業所として認定されている企業です。常にご依頼者さまの気持ちに寄り添い、心のこもった丁寧なサービスをご提供しています。家の中が物であふれている、スムーズに片付けが進まないなどのお悩みがあれば、ワンズライフまでお気軽にご相談ください。
おすすめ記事
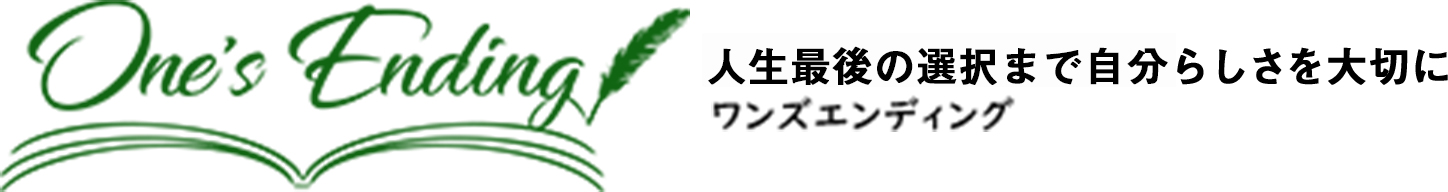




 " alt="ゴミ屋敷からの引っ越し 片付け方と業者依頼のポイントをご紹介">
" alt="ゴミ屋敷からの引っ越し 片付け方と業者依頼のポイントをご紹介"> " alt="片付けられない症候群の特徴と改善策とは?部屋を片付けられない原因は病気や障害かも?">
" alt="片付けられない症候群の特徴と改善策とは?部屋を片付けられない原因は病気や障害かも?">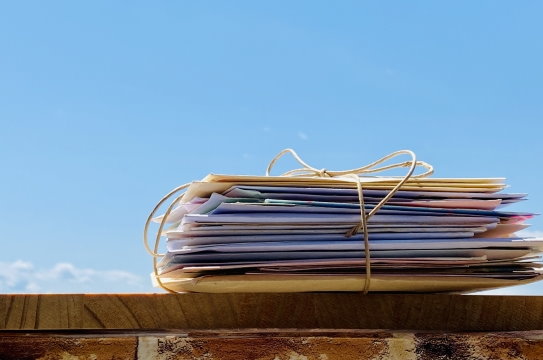 " alt="片付けられない親と喧嘩せずに生前整理をするコツ">
" alt="片付けられない親と喧嘩せずに生前整理をするコツ"> " alt="失敗しない、ゴミ屋敷片付け業者の選び方のポイント">
" alt="失敗しない、ゴミ屋敷片付け業者の選び方のポイント"> " alt="遺品整理や片付けで不要になった洋服・古着おすすめの寄付先一覧">
" alt="遺品整理や片付けで不要になった洋服・古着おすすめの寄付先一覧"> " alt="汚部屋になりやすい人の特徴7つ。汚部屋を脱出する方法はある?">
" alt="汚部屋になりやすい人の特徴7つ。汚部屋を脱出する方法はある?">



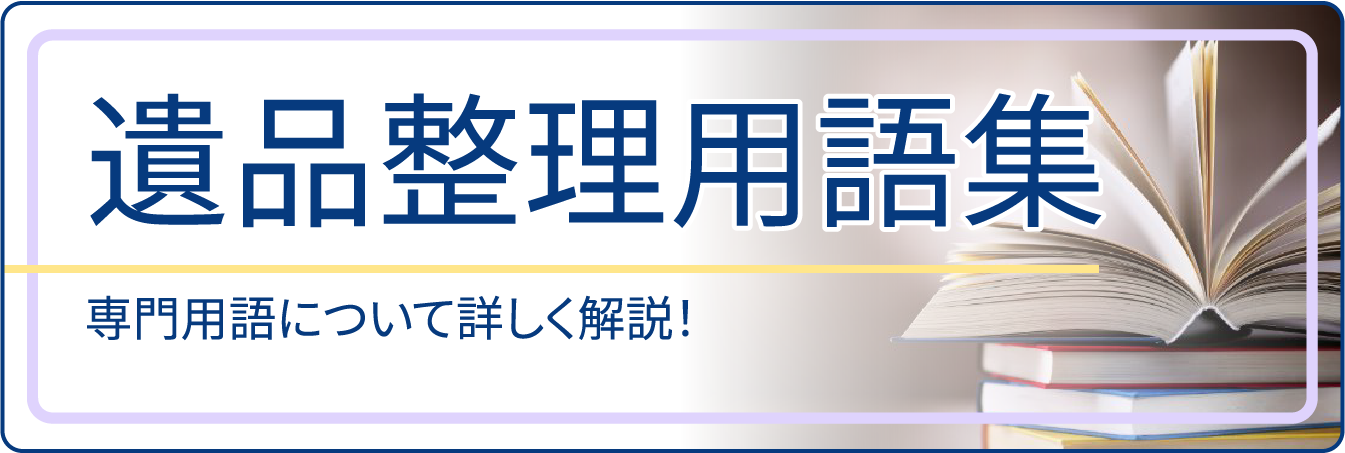





 " alt="セルフネグレクトとは?原因や心理、対策事例で孤独死を防ぐ">
" alt="セルフネグレクトとは?原因や心理、対策事例で孤独死を防ぐ">