
2019.04.18
【コラム】あの人に、こころ寄せるひとときVol1.~祖母が教えてくれたこと~
人は生まれ来て、そして必ず去ってゆく。
人生とは、そして時間とは――。
この特集コラムでは、大切な人との想い出の品にまつわる
ストーリーをお届けしてまいります。
皆さんの心の中に住んでいる、
大切な人との絆を
感じ取っていただければ幸いです。
ふたりだけの習字教室
「ほう、上手な字を書けるようになったもんじゃ。宏文はええ子になったのう」
祖母はいつも、我が家へ来るたびに壁に貼られた習字を見て僕を褒めてくれていた。そしていつもの口癖は、「宏文はええ子になった」だった。小学校五年生になった僕は、もうそれがいい加減恥ずかしくなっていた。
「もう、僕は赤ちゃんじゃないけえ、ええ子って言わんとって」
思春期を迎えつつあった僕は、ある日祖母に向かってそう言ったことがある。祖母は一瞬、驚いた顔をしたが、すぐに笑顔になってこう言った。
「そうよのう、宏文はなんぼになったんかの?」
少し忘れっぽくなってきた祖母に、母がため息をつきながら「五年生になったんよ。十歳」と言った。すると祖母はいつも、眼鏡の奥の細い目をさらに細くして「そうかぁ、宏文、大きゅうなったんじゃのう」と嬉しそうに言った。
幼い頃、家の近くの習字教室に通っていたのだが、ちっとも上手くならなかった。そこで僕は、小学三年生の時から一年ほど週に一回、クルマで十五分ほどの母の実家に祖母の手ほどきを受けに行っていたのだった。祖母は昔、習字の先生をしていたのだという。祖父が早くに亡くなったせいで、祖母は女手一つで三人の子ども達を育てなくてはならなかったからだ。
「心」を大切にする、ということ
祖母の部屋はいつも、墨汁と紙の匂いがしていた。六畳ほどの狭い部屋だったが、いつも整理整頓がされていて、一輪挿しには花が生けられていた。祖母の教えは、とても優しかった。僕はきれいな字を書くと、祖母はいつも褒めてくれた。
「宏文は上手になるのが速いのう」
習字の先生は厳しかったので、祖母に褒められるとなんだか幸せな気持ちになれた。
しかし、一度だけそんな祖母にひどく叱られたことがある。それは、僕が祖母の硯を机の上に乱雑に置いた時のこと。どん、と少し大きな音がした。その時の僕はおそらく、今日も祖母から習う習字が面倒だと思っていたに違いない。
「習字がいやなら、今すぐ帰りなさい!」
僕は生まれて初めて、祖母の険しい顔を見た。それは、僕が見たどんな大人よりも怖かった。
「ええか、宏文。この習字道具にはいろんな人の心がこめられとるんよ。これを作った人がいて、これを買ってくれたおじいちゃんがいて、それを今まで大事に使ってきた私がいる。それを宏文はぜんぶ粗末にしようとしとる。習字をほんまにしとうないんなら、やめたらええ」
僕は、祖母に初めて叱られた怖さと申し訳なさで涙が止まらなかった。ごめんなさい、ごめんなさい、と何度も言ったことを覚えている。
それから一週間後、僕は次の手ほどきから祖母の教えを真剣に聞くようになった。祖母も以前より褒めなくなったが、僕の習字はみるみるうちに上達し、六年生の終わり頃には賞状の枚数は二十枚を超えた。
その後、僕は実家を離れ、大阪で暮らすようになって忙しい日々を送るようになり、帰省もあまりできなくなっていた。
最期の言葉と、贈りもの
それは、僕が社会人になって五年目の夏だった。
祖母の容態があまりよくないという報せを聞き、大阪から実家のある広島へすぐに帰省した。
久しぶりに会った祖母は、ひどく痩せていた。もはや自宅で過ごす状態になっていたのだ。
「おばあちゃん」
祖母は僕の顔をずっと見ていたが、やっと僕だとわかったようだった。
「宏文じゃけど、わかる?」
祖母は何も言わず、僕の顔をずっと見ていた。
「おばあちゃんのおかげで、いま、子どもたちに習字を教えとるんよ」
祖母は、少し微笑んだ。僕は祖母の手を握った。少しだけ僕よりもつめたくて、でも柔らかな温もりがあった。
「じゃあ、僕、行くから」
僕が背を向けると、祖母は初めて口を開いた。そして、それが僕への最期の言葉となった。
「宏文。しっかり勉強せえよ」
それから二週間後、祖母は眠るように息を引き取ったという。長男の嫁への「ありがとうね」のひとことを遺して。
祖母の供養が終わった後、僕宛に母から形見が届いた。風呂敷を紐解くと、あの硯に加えて、祖母が大切にしていた墨と筆と水差しが出てきた。これらは宏文に、と祖母が言ってくれていたらしい。
おばあちゃん、今度は大切に使うからね。宝物をありがとう。
おすすめ記事





 " alt="【コラム】あの人に、こころ寄せるひとときVol.5~元営業マンとエンディングノート~">
" alt="【コラム】あの人に、こころ寄せるひとときVol.5~元営業マンとエンディングノート~"> " alt="だからこそ、生前整理は大切!実録「想定外の遺品たち」">
" alt="だからこそ、生前整理は大切!実録「想定外の遺品たち」"> " alt="【コラム】あの人に、こころ寄せるひとときVol3. ~母親の形見分けに集まった、あるきょうだい達の話~">
" alt="【コラム】あの人に、こころ寄せるひとときVol3. ~母親の形見分けに集まった、あるきょうだい達の話~"> " alt="遺品整理のドラマをご紹介~「星降る夜に」「ムーブ・トゥ・ヘブン」「dele」">
" alt="遺品整理のドラマをご紹介~「星降る夜に」「ムーブ・トゥ・ヘブン」「dele」">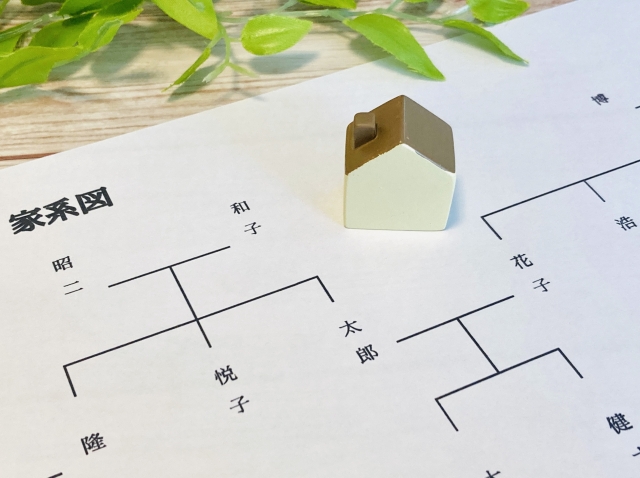 " alt="家系図を自分で作成する方法~調べ方や書き方のポイント">
" alt="家系図を自分で作成する方法~調べ方や書き方のポイント"> " alt="【コラム】あの人に、こころ寄せるひとときVol.2 ~とあるゴミ屋敷の話~">
" alt="【コラム】あの人に、こころ寄せるひとときVol.2 ~とあるゴミ屋敷の話~">









 " alt="若い世代に増えているミニマリスト ミニマリスト=終活ではない理由">
" alt="若い世代に増えているミニマリスト ミニマリスト=終活ではない理由">