
2017.10.05 (2024.04.19 One's Ending編集部 加筆)
孤独死とは-原因と対策 防止するためにできること-
「孤独死は高齢者の問題だ」そう思ってはいませんか?
孤独死は、高齢者にだけ起こることではありません。
働き盛りの世代の方にも孤独死が起こっています。
今後は「孤独死がありふれた死となる」と指摘している専門家もいるほど、現在では深刻な社会問題のひとつとなっています。
今回は、孤独死が増えている原因と対策について解説します。
孤独死とは
孤独死には、国として共通した定義はありません。
平成8年に広辞苑で初めて「孤独死」が明記され、そこには「看取る人もなく、一人きりで死ぬこと」と記されています。
一方で孤独死について、警察の死因統計では「変死」として扱われることが多く、行政においては「孤立死」と表現されることが増えてきています。
この記事の中では、孤独死を「誰にも看取られない状態で息を引き取り、そのまま一定期間発見されなかった状態」と定義した上で、孤独死について深く考えていきたいと思います。
現代の日本において孤独死が増えている背景
なぜ、日本において孤独死が増加しているのでしょうか?
その原因を社会的な観点から解説していきます。
単身世帯の増加
ひと昔前の時代までは、サザエさんのように祖父母から孫までの3 世帯同居生活が当たり前でした。
しかし現代では、親と子が離れて暮らす核家族や、結婚をせず、さまざまな事情があって家族を持たない単身者が増加傾向にあります。
単身世帯については全世代で増加傾向にありますが、その中でも特に懸念されているのが「高齢者の単身世帯が増えている」ということです。
以前は、たとえ高齢者がひとりで暮らしていても、親戚関係にある家族が定期的に訪問して、健康状態や日々の様子を確認していました。
しかし、近年はそういった親戚づきあいも希薄となりつつあります。
また、友人同士の付き合いも希薄化してきているのが現状です。
単身で暮らし、友人や訪問する家族もなく、社会とのかかわりが遮断されている中、次第に衰弱し、誰にも発見されないまま孤独死してしまう方が増えているのです。
雇用体制の変化
かつては、一度就職するとそのまま定年まで勤めあげる「終身雇用制度」がほとんどの会社で採用されていて、仮に社員が出社しなかった場合は、すぐに会社の方が自宅を訪問し、無事かどうかを確認するケースがよく見られていました。
しかし現代では、非正規雇用や派遣といった雇用体制で仕事をする人も増え、終身雇用制度はなくなりつつあります。
そのため、企業側も社員一人ひとりに対し、欠勤したからといってすぐに自宅へ確認しにいく手間をかけなくなりました。
その結果、会社勤めで仕事をしていても、周囲の人が知らない間に孤独死に至ったというケースが増加傾向にあります。
また、正規雇用でないためにお金がなく、経済的な問題で生活が困窮して、体調を崩した結果孤独死に至るというケースもあります。
周囲とのコミュニケーションが希薄
以前は複数人で楽しむものという風潮があったカラオケや焼き肉ですが、ニュースや雑誌で「ひとり○○」「おひとりさま」という言葉が取り上げられた影響もあり、最近は「一人カラオケ」「一人焼き肉」もスタンダードになりつつあります。
そのため、一人での生活そのものを楽しもうとする方が増え、以前と比べて他者と積極的にコミュニケーションを取る機会が減りつつあるのです。
一人の生活を楽しむことに問題はありません。
しかし、人間は毎日一人の生活に慣れすぎると、徐々に他人とコミュニケーションを取ることが億劫になります。
また、近年のインターネットの普及により「ネット上でのコミュニケーション」は積極的にとられるようになった一方で「直接顔を合わせてのコミュニケーション」は希薄になってきているのです。
その結果「オンラインでコミュニケーションは取っているのに、隣近所には誰が住んでいるかもわからない」という極端な状態になってしまうのです。
そして、何かあったときに発見してもらえずに、孤独死に至るというケースも増えています。
孤独死に陥りやすい人の特徴
孤独死は高齢者だけの問題ではありません。
知らず知らずのうちに、孤独死のリスクを高めてしまっている人は意外と多いのです。
孤独死に陥りやすい人には、以下のような特徴があります。
一人暮らしの高齢者
高齢になると、定年退職や配偶者の死などにより、人間関係が希薄になり、孤立しやすくなります。
また、身体的な衰えや病気によって、外出や交流が難しくなっていきます。
これらの要因によって、高齢者は自宅で一人で過ごす時間が長くなり、孤独死のリスクが高まるのです。
また、高齢者は突然体調を崩すことも多いです。
家族と同居していたら防げたのに、一人暮らしだったためすぐに発見されず、命を落としてしまうケースが後を絶ちません。
慢性的な疾患がある
慢性的な疾患を抱えている人も、孤独死のリスクが高くなります。
病気の悪化や合併症によって、突然死する可能性があるからです。
病気や怪我で寝たきりになった場合も、一人で生活を続けることが難しくなるため、そのまま亡くなってしまうケースが少なくありません。

経済的に困窮している
失業や借金、貧困などによって経済的に困窮している人は、自分の生活状況に恥ずかしさや劣等感を感じてしまう傾向があります。
人から見下されることを恐れるあまり、人との交流を断って、自分の中に閉じこもってしまうことがあるのです。
また、経済的に困窮している人は、住居や食事、医療などにおいて、十分なサービスや支援を受けられないことも多いです。
例えば、老人ホームや介護施設に入居するためには、高額な費用がかかります。
経済的な理由で入居を断念するケースが多く、それが孤独死につながることもあります。
人付き合いが苦手
人付き合いが苦手な人も孤独死のリスクが高まります。
親族や友人、ご近所付き合いが苦手なあまり、孤立してしまうためです。
人付き合いが苦手な人は、自分に自信がなかったり、人とのトラブルやストレスになるようなことを避けてしまう傾向があります。
また、自分の感情や悩みを誰にも打ち明けられないため、人からの助けや支えを得られないことも少なくありません。
孤独死を防ぐための具体的な対策
孤独死を防ぐためには、日頃から健康管理や周りの人との交流をはかり、孤立しないことが大切です。
また、様々な見守りサービスやアプリもあるので、活用していくことを検討してみるのも良いでしょう。
孤独死を防ぐための具体的な対策は、以下のようなものがあります。
社会とのつながりを作る
社会とのつながりを作ることは、孤独死を防ぐ最も基本的な対策です。
親族や友人と定期的に連絡を取り合うだけでなく、できれば直接会って一緒に食事をしたり、話をしたりしましょう。
趣味のサークルやボランティアなどの活動に参加して、地域や社会とのつながりを作ることも孤立化を防げます。
同じ趣味や関心を持つ人と交流することで、孤独感が薄れ、ストレスを軽減できます。
町内会や自治会への参加も有効です。
普段からご近所さんと交流をしておくことで、何かあっても早期に発見してくれる可能性が高まります。
健康管理をしっかり行う
健康管理をしっかり行うことも、孤独死を防ぐために必要な対策です。
健康状態が悪化すると、自立した生活を送ることが難しくなり、孤独死のリスクが高まってしまいます。
健康管理をするためには、以下のことに注意しましょう。
・定期的に健康診断を受ける
・栄養バランスのとれた食事を摂る
・睡眠時間や水分補給を十分にも気を付ける
・適度な運動や日光浴をする
・ストレスや不安をため込まない
健康管理の基本は、定期的に健康診断を受け、日頃から栄養バランスのとれた食事を摂ることです。
また、十分な睡眠をとることや水分補給も忘れないように気を付けましょう。
そして、適度な運動も大事なのですが、家で運動するだけでなく、できるだけ外に出て日の光を浴びるように心掛けましょう。
定期的に近所をお散歩をするだけでも運動になります。
心の健康を保つためにも、ストレスや不安をため込まないことも重要です。
仲間と楽しめるような趣味を持ち、悩みを相談できる人ができると良いでしょう。
支援制度やサービスを利用することも検討する
孤独死を防ぐための支援制度やサービスを利用することも、有効な対策です。
支援制度やサービスは、以下のようなものがあります。
・地域包括支援センターの見守りサービス
・民間の見守りサービス
・老人ホームや介護施設への入居
市区町村や民間の見守りサービスを利用することで、定期的に安否確認や訪問をしてくれたり、緊急時に駆けつけてくれたりします。
老人ホームや介護施設、サービス付き高齢者向け住宅などに入居することも有効です。
一人暮らしではなく、他の高齢者やスタッフとの交流ができる環境に移ることで、孤独死のリスクを大幅に減らせます。
また、電気ポットやエアコンなど、しばらく利用がないことを検知して、家族などに報告する遠隔機能付家電も売り出されています。
これらの方法を組み合わせて、自分や家族の孤独死を防ぐための対策を検討しましょう。
孤独死に遭遇してしまった時にすべきことは?
もしも身近で孤独死が起き、その現場に遭遇してしまった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
はじめにするのは「すぐに警察へ通報すること」です。
明らかに孤独死であったとしても、警察では死因が特定されるまでは「異状死」として扱われ、強盗や殺人といった事件性がないかの調査が行われます。
これらの調査を行う上で、当時の内部の様子も重要な情報源となる可能性があるため、孤独死に遭遇してしまった場合、故人の荷物には一切手を触れないように気を付けましょう。
また、警察による現場検証と並行して、ご遺族や保証人へなどに連絡が入ります。
その後、死因の特定や事件性の有無についての調査が終了すると、ご遺体を引き受ける人が決まり、葬儀の手配などが行われるという流れです。
このように、万が一孤独死の第一発見者となった時は、大まかな流れを把握しておくことで、急な出来事でも落ち着いて対応できます。
孤独死現場を発見した際の対応や一連の流れについては、ワンズエンディングのこちらのコラムページでも解説しています。
【関連記事】孤独死を発見した時の対応を解説
まとめ
孤独死は、周囲とのコミュニケーションが希薄化することで発生しやすくなります。
孤独死を防ぐためには、たとえ苦手意識があったとしても言葉をかけ合い、地域で暮らしている人一人ひとりが、自分から周囲と積極的にコミュニケーションを取ることが大切なのです。
もし、家族や親せきが一人暮らしをしている場合には、定期的に連絡を取るよう心がけてください。
写真や動画を送ったり、ビデオ通話をしたりするのがおすすめです。
また「遠くの親戚より近くの他人」ともいわれます。
近所の人と町中で出会ったら積極的に挨拶をして、お互いの顔を覚えるようにしていきましょう。
このような小さなコミュニケーションの積み重ねが、社会全体で孤独死を防いでいく第一歩につながります。
人と出会うことがあったら、明るく元気に笑顔で話しかけていきましょう。
当社ワンズライフでは、孤独死現場の遺品整理のご依頼やご相談も承っております。
遠方に住まわれていて当日の立ち合いが難しい親族の方や、不動産のオーナーさまからご依頼、ご相談もお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。
【当社サービス】ワンズライフ
おすすめ記事
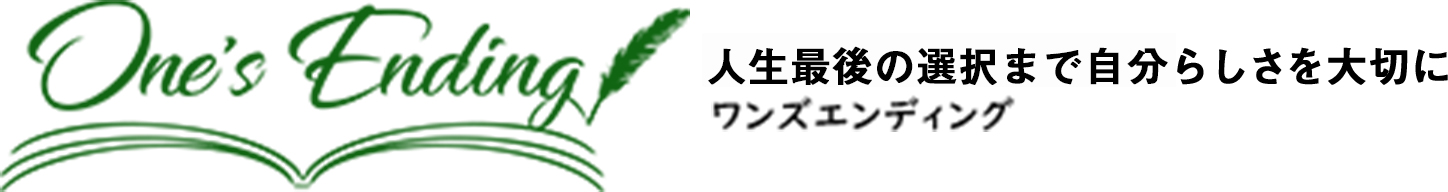




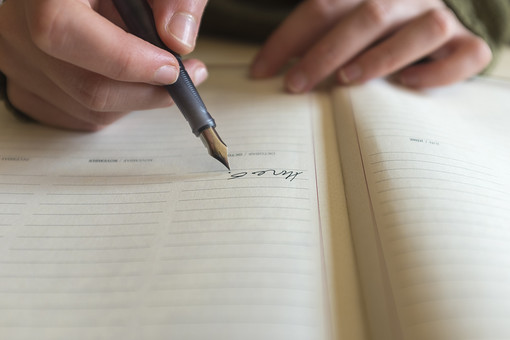 " alt="【コラム】あの人に、こころ寄せるひとときVol.5~元営業マンとエンディングノート~">
" alt="【コラム】あの人に、こころ寄せるひとときVol.5~元営業マンとエンディングノート~">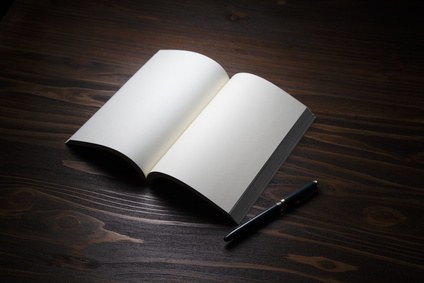 " alt="エンディングノートとは何?メリットやおすすめの選び方と書き方を解説">
" alt="エンディングノートとは何?メリットやおすすめの選び方と書き方を解説"> " alt="芸能人・有名人の終活に学ぶ!いつから始める?自分らしい終活とは">
" alt="芸能人・有名人の終活に学ぶ!いつから始める?自分らしい終活とは">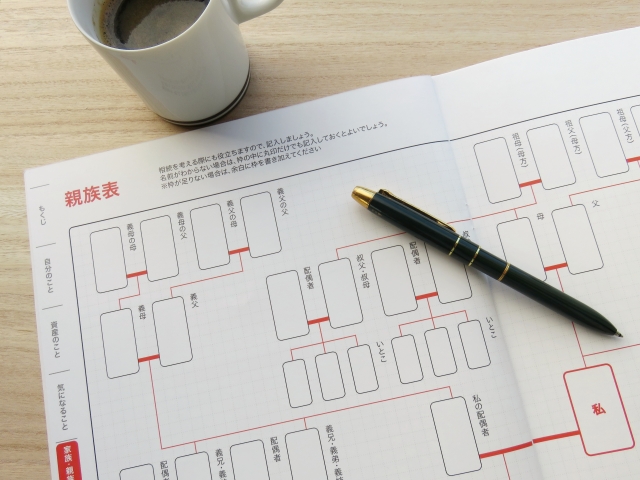 " alt="エンディングノートを親に勧めたいなら">
" alt="エンディングノートを親に勧めたいなら"> " alt="おひとりさまの終活とは ポイントを解説">
" alt="おひとりさまの終活とは ポイントを解説"> " alt="尊厳死と安楽死との違い~定義や日本における現状">
" alt="尊厳死と安楽死との違い~定義や日本における現状">



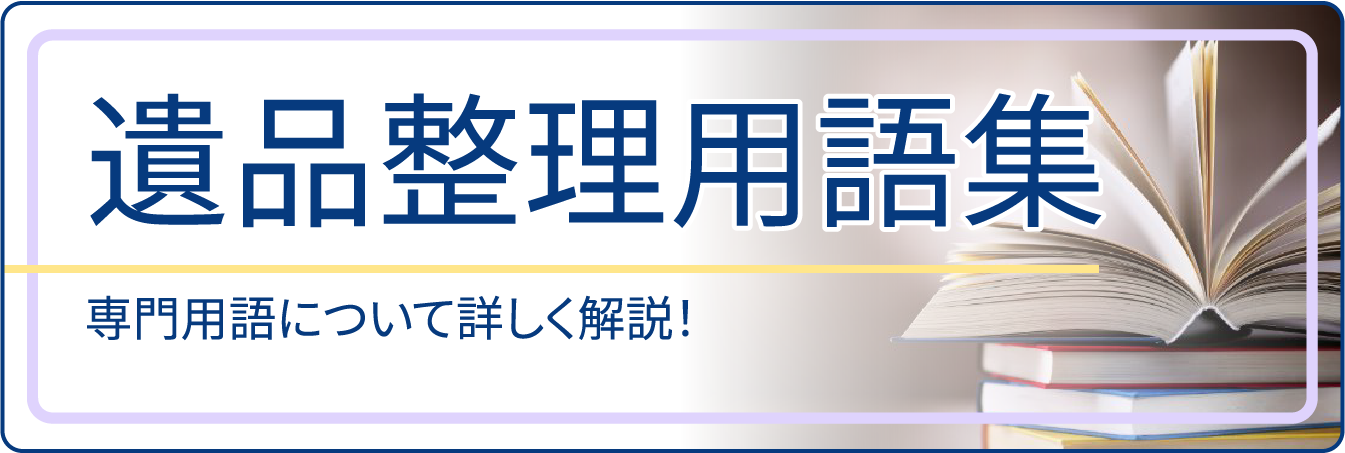





 " alt="映画『お終活 熟春!人生、百年時代の過ごし方』に見る終活">
" alt="映画『お終活 熟春!人生、百年時代の過ごし方』に見る終活">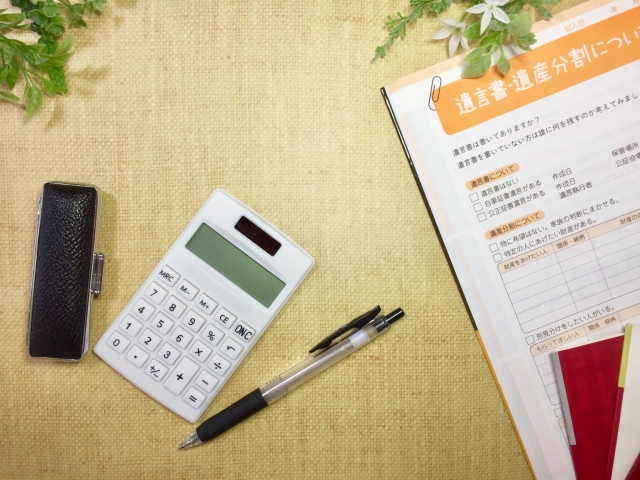 " alt="終活にお金は必要?準備に費用が必要なものを解説">
" alt="終活にお金は必要?準備に費用が必要なものを解説"> " alt="コレクター(オタク)の終活でやっておきたい準備">
" alt="コレクター(オタク)の終活でやっておきたい準備">