
2019.08.23 (2024.10.28 One's Ending編集部 加筆)
現代社会が見える! 遺品整理の最新事情2024
近年、超高齢化社会によって「終活」に取り組む方が増えています。
遺品整理や生前整理も、よく聞く言葉になりました。
そこで今回は、現代社会における遺品整理の最新事情を探ってみたいと思います。
近年、超高齢化社会や核家族化の影響で単身高齢世帯が増えています。
特に男性の高齢者は家族や近所の方と直接的な交流が少なくなる方が多いです。
そして、インターネットを活用する高齢者が増えることでデジタル遺品が増加しています。
また、遺品整理を業者に依頼する方が増える一方で、契約トラブルも増加傾向です。
現代特有の事情やトラブル回避策を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
日本の高齢化の現状と遺品整理を取り巻く環境
超高齢化社会といわれる日本ですが、具体的にどのような状況になっているのでしょうか?2024年に内閣府が発表した「令和6年度版高齢社会白書」 を見ると、日本の現状が見えてきます。(※)
日本における高齢化の現状
「高齢社会白書」によると、2023年10月1日の時点で、65歳以上の方は3,623万人で、総人口に占める割合が29.1%です。
そして、高齢者の6割以上が夫婦2人、もしくは1人暮らし世帯です。
特に1人暮らしの高齢者は男女ともに増加傾向にあります。
それに伴い高齢者の孤独死も増えていくことが予想されます。
親族が遠方に住んでいる場合は、遺品整理業者に依頼しなければならないケースも増えていくことでしょう。
遺品整理を業者に依頼する方は増加傾向
昨今、亡くなった方の遺品整理を業者に依頼する方が増えています。
高齢になると認知機能が低下して、片付けられなくなる方もいらっしゃいます。
特に認知症などで外出の機会が減ったり人とコミュニケーションを取らなくなったりすると、身の回りのことがおろそかになり、遺品整理業者や特殊清掃業者に依頼しなければならないほど、家がゴミ屋敷になるパターンも多いのです。
遺品整理業の認知度が上がったもう1つの要因
実はもう1つ遺品整理業者が注目をされた理由として、韓国ドラマ「ムーブ・トゥ・ヘブン:私は遺品整理士です」 の影響が挙げられます。
このドラマは題名の通り、遺品整理業を営む家族を題材としていて、2021年5月14日からNetflixで独占配信されました。
日本でも大ヒットした「愛の不時着」に出演していたタン・ジュンサンが主演ということで、終活にあまり縁のなかった若い女性にも遺品整理業が認知されるきっかけになりました。
この他にも様々なメディアで遺品整理が取り上げられるようになっています。
※出典:内閣府「令和6年版高齢社会白書」
最近よく聞く「デジタル終活」って?

最近増えているのが、「デジタル終活」です。前述の「高齢社会白書」によると、インターネットを活用する高齢者が増加傾向にあります。
スマホやパソコンには個人情報がたくさん詰まっていて、家族にも見せていなかったり取り扱いに困ったりするものがあります。
次のものは万が一持ち主が亡くなったときに、「デジタル遺品」になり得るのです。
・写真
・メールのやり取り
・スケジュール
・ネットバンキング
・SNS
・サブスクリプションサービス
ネットバンキングやサブスクリプションサービスなどを解約するにはIDやパスワードが必要です。
しかしながら、IDやパスワードをメモに残している方は少数でしょう。また、亡くなったあと写真やメールのやり取りなどの個人情報をどのように処理してほしいのかを考えたり家族に伝えたりすることも必要です。
デジタル終活はじっくりと時間をかけて計画的に行うことをおすすめします。デジタル終活については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:デジタル遺品とは?パソコンやスマホに残るデータの遺品整理・生前整理
生前整理・遺品整理にフリマアプリを使う人が増えている!?

最近、スマホのフリマアプリを利用して生前整理や遺品整理する人も増えているのをご存じでしょうか。
フリマアプリとは、写真や希望価格とともに売りたい商品を投稿すると、購入希望者とやり取りや売買ができるサービスです。
実際に「遺品整理」や「生前整理」で検索すると、アプリ上にさまざまな品物が出てきます。
リサイクルショップでは買い取ってもらえないようなものでも欲しい人さえいれば売れること、リサイクルショップ等より高く売れる傾向があることが人気の要因なのでしょう。
時間をかけてじっくりと整理をしたい方にはおすすめの方法ですが、発送ややり取りの手間がかかるため、急ぎたい方には不向きかもしれません。
タンス預金の新札発行による影響や遺品整理での注意点

2024年7月に新札が発行されました。
新札発行の主な目的は偽造の防止とされていますが、タンス預金のあぶり出しも目的の1つではないかといわれています。
古いお札を新しいお札に入れ替える過程で、タンス預金の一部でも消費や投資に回してもらいたいという思惑もあると考えられます。
実際にタンス預金の一部を消費に回したという方は多いのではないでしょうか。
タンス預金には、すぐに使えるといったメリットがあるため、悪いことではありません。
しかし盗難や紛失のリスクに加えて、相続トラブルになりやすいといったデメリットがあります。
必要以上の金額をタンス預金してしまうとリスクが高くなるのです。
新札発行によってタンス預金が多少減る可能性もありますが、遺品整理の際は早急にタンス預金があるかどうか確認しなければなりません。
タンス預金をする傾向が特に強いのは高齢者です。
遺品整理では遺族も存在を知らなかったタンス預金が発見されることがあります。
当社ワンズライフでも故人様のタンスの裏から出てきた2つの金庫から合計2億円の現金を発見したことがあります。
もともとご依頼者様は「金庫の中身は何もないので捨ててください」と、おっしゃっていました。
しかし、何かあってはいけないと思い、念のためにご依頼者様の立ち会いのもとで金庫を開けさせていただいたところ、2億円もの現金を発見したのです。
これは日経新聞にもとりあげられてニュースにもなりました。
もしそのまま捨てられていたらと考えると、大変恐ろしくなります。
こういうケースがあるからこそ、信頼できる業者に依頼する必要があると言えるでしょう。
【関連記事】タンス預金は相続税や贈与税の対象になるのか
遺品整理サービス業者によるトラブルも増加している!?

総務省の実態調査によると、遺品整理や処分などを行うサービスへの需要が増えています。(※1)
しかし同時に、遺品整理サービス全体に関して相談件数も同時に増えつつあるのです。
実際のところ、遺品整理サービスに関しては、直接的に監督する行政機関がないことも相談の増加に拍車をかけていると言えます。 ちなみに、最も多い相談内容は、契約と解約について(約70%)、次に価格について(約36%)。
たとえば、見積もり時に急かされて契約したものの、納得できなかったため申し出たら高額なキャンセル料を請求された、依頼時に処分しないように伝えていたものを、勝手に処分や売却されたなどといった相談まであります。
トラブルの根本的な要因としては、双方の確認不足や詳細な契約書が取り交わされていないことが挙げられます。
また、一部悪質な業者が存在することも事実です。そこで、トラブルを避けるために、気をつける7つのポイントをご紹介します。
(1)複数の業者から見積もりをとる
業者をすぐに決めず、2~3社の相見積もりを依頼しましょう。
相場がわからないまま契約しないように、複数の業者の見積もりをとって作業量に見合う常識的な価格の目安を知っておくのをおすすめします。
見積もりを依頼する際には、見積り料や出張料、キャンセル料などが発生するかどうかも確認しましょう。(当社ワンズライフは出張お見積り無料、キャンセル料も発生しません)
(2)見積書の明細をチェックする
見積もりに明細が書かれていない業者は、料金のトラブルが起きやすいためおすすめできません。
複数の見積書を見比べて、最終的にどの業者と契約するか考えましょう。
どの作業をいくらでしてくれるのか、追加料金に関する内容、作業のカウント単位は日数なのか時間なのか個数なのかなど、細かい項目を1つずつ比較しましょう。
(3)安すぎる業者には用心する
あまりにも安すぎる業者には注意しましょう。
不用品を適正な処理をしないまま捨てていたり、あとで追加料金を要求したりするケースもあるからです。
する 場合もあるからです。
また、安すぎる価格設定の業者はスタッフ教育に力を入れていないことが往々にしてあります。
丁寧な対応を望む場合には、遺品整理に携わる者として必要なモラルやマナー、スキルを兼ね備えた人材を育成している、信頼できる業者を選びましょう。
(4)遺品整理士の資格をもつ業者を優先しましょう
遺品整理士は「一般社団法人遺品整理士認定協会」によって養成されている遺品整理のスペシャリストです。
遺品整理士の資格を保有しているということは遺品整理に関して正しい知識と技術を学んだということ。
遺族の気持ちに寄り添いながら作業をするなどといった配慮も可能です。
また、遺品整理士認定協会では、遺品整理士の資格をもつ優良企業をホームページ上で紹介しています。全国の遺品整理業者一覧が掲載されていますので、こちらを参考にするのもおすすめです。
(5)必要品と不要品を事前に分けておくとベスト
トラブルを防ぐためにも、業者を呼ぶ前に大切な遺品と処分して欲しいものを分けておくと安心です。
移動できない重い家具などには貼り紙をしておきましょう。
また、自分たちでも整理できそうなものは自分たちで行うことで、業者へ支払う費用を抑えることができます。
(6)遺品を買い取りやリサイクルできる業者を選ぶ
「古物商許可」などの資格をもち、遺品の買い取りやリサイクルを行える業者を選びましょう。
(7)トラブルになったら行政へ連絡する
契約を強引に迫る業者やキャンセルの際にトラブルになったときはいつでも、居住地の消費者生活センターや警察に連絡しましょう。局番なしで「188(いやや)」に電話すると、最寄りの消費生活相談窓口につながります。 (※2)
※1出典:総務省「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」
※2出典:独立行政法人国民生活センター「全国の消費生活センター等」
まとめ
今回は、現代社会における生前整理・遺品整理についてご紹介しました。
単身高齢者世帯が増えることで、遺品整理サービスの需要は今後ますます増えていきます。
それに伴って悪質な業者によるトラブルも増えていますが、今回紹介したポイントを抑えてトラブルを未然に防ぎましょう。
時代や価値観がどのように変わろうとも、当社ワンズライフではお客様が遺品の扱いに関してご安心いただけるようにひとつずつ目視で仕分け作業を行ってまいります。
おすすめ記事
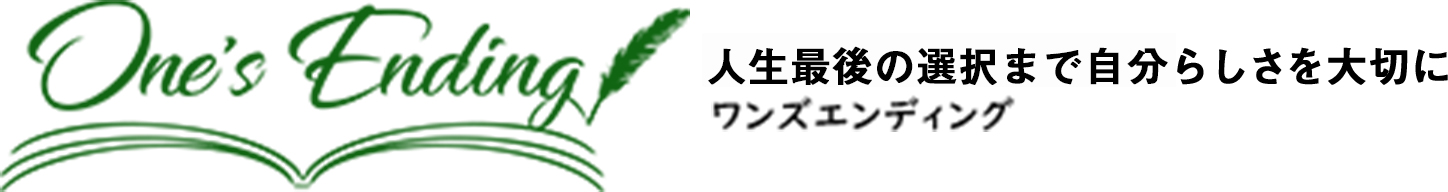




 " alt="遺品整理業者って、不用品回収や便利屋とどう違うの?">
" alt="遺品整理業者って、不用品回収や便利屋とどう違うの?"> " alt="孤独死を発見した時の対応を解説">
" alt="孤独死を発見した時の対応を解説"> " alt="遺品整理で処分に困る遺品とは?供養・売却・処分方法">
" alt="遺品整理で処分に困る遺品とは?供養・売却・処分方法"> " alt="遺品整理は自分でする?業者に依頼?体験談から考えるオススメのやり方">
" alt="遺品整理は自分でする?業者に依頼?体験談から考えるオススメのやり方"> " alt="遺品整理や片付けで不要になった洋服・古着おすすめの寄付先一覧">
" alt="遺品整理や片付けで不要になった洋服・古着おすすめの寄付先一覧"> " alt="遺品の車はどうすればいいのか~相続手続きや売却・処分方法を解説">
" alt="遺品の車はどうすればいいのか~相続手続きや売却・処分方法を解説">



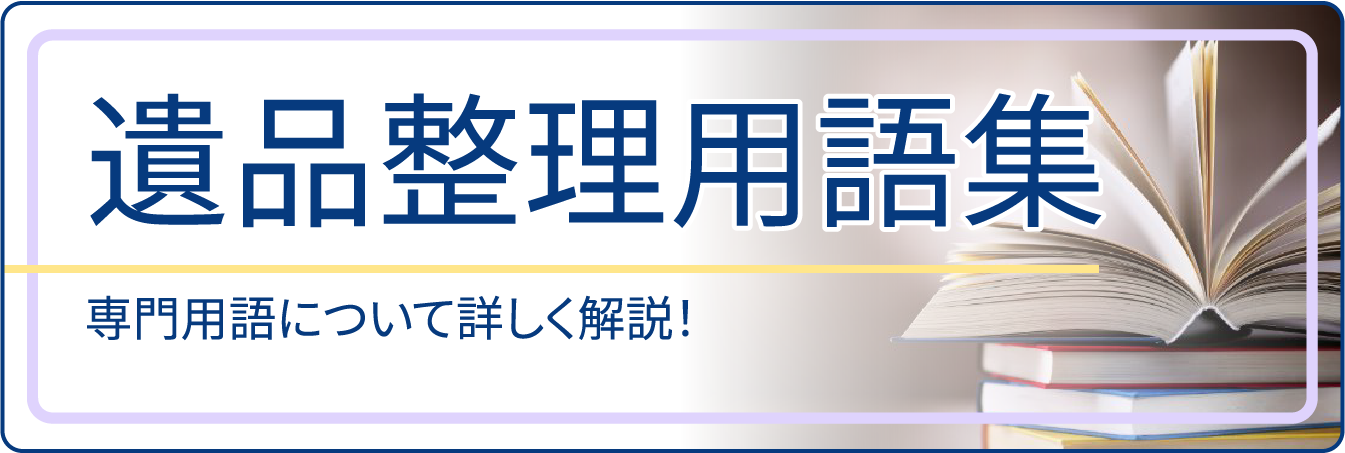





 " alt="賃貸物件が事故物件に?大家さんが知っておきたいクリーニング方法とは">
" alt="賃貸物件が事故物件に?大家さんが知っておきたいクリーニング方法とは"> " alt="遺品整理業者を選ぶときの注意点~遺品整理の流れやおすすめの時期をご紹介">
" alt="遺品整理業者を選ぶときの注意点~遺品整理の流れやおすすめの時期をご紹介"> " alt="身寄りのない人が亡くなられた場合はどうなるのか">
" alt="身寄りのない人が亡くなられた場合はどうなるのか">