
2017.05.09 (2025.02.27 One's Ending編集部 加筆)
遺品整理業者を選ぶときの注意点~遺品整理の流れやおすすめの時期をご紹介
遺品を整理しなければならないとき、思い出の品々を前に気持ちの整理がつかず、途方に暮れる方も多いのではないでしょうか。
悲しみが癒えるまで待ち、ゆっくり遺品整理を進められたらよいのですが、早めに遺品整理をしなければならないケースもあります。
この記事では遺品整理を行ったほうがよい時期や作業の流れについて、詳しく解説していきます。
また、遺品整理業者に依頼することについてのメリット・デメリットや、選ぶときの注意ポイントもお伝えします。
自力で遺品整理をするのは大変だけど、業者に依頼するのは不安だ、と感じられている方は、ぜひ参考にしてください。
遺品整理に適した時期
遺品整理を行う時期に正解はありません。
しかし、遺品整理を始めるのに適した時期はありますので、解説していきます。
葬儀・告別式終了後
あまり多くはありませんが、葬儀や告別式が終わってすぐに遺品整理をする方もいます。
遺族や親族の多くが遠方に住んでいると、予定を合わせて集まるのが大変だからです。
次に集まる日程が組めない場合は、親族が揃う葬儀、告別式後のタイミングで遺品整理を行うのもよいでしょう。
四十九日のあと親族が集まるタイミングで
仏教の考え方では、故人が亡くなってから49日目に極楽浄土に旅立つことになっています。
故人は四十九日を迎えるまではこの世に存在しているので、亡くなったあとすぐに遺品整理をするのは早すぎると感じられる方もいるため、四十九日法要を終えてから始める方が多い傾向にあります。
また、遺品整理は相続人などの親族が集まるタイミングで行うのがおすすめです。
遺品に対する思い入れは、ご遺族であっても故人との関係や思い出によって異なります。
後からトラブルにならないように、1人で勝手に始めず親族が集まるときに遺品整理をしましょう。
遺品整理は肉体的にも精神的にも負担が大きいので、親族一同で協力して行うのをおすすめします。
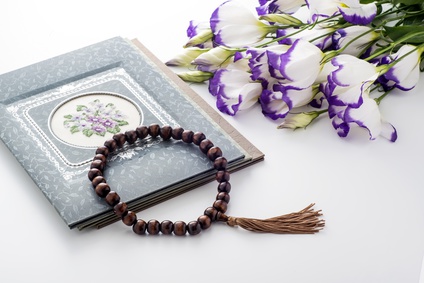
各種手続きの終了後
家族が亡くなるとさまざまな手続きが必要です。
「死亡してから〇日以内」と期限が定められていることも多いため、手続きが落ち着いてから遺品整理を始める方もいます。
以下は家族が亡くなったあとに必要な手続きの一例です。
・死亡届
・ガス、電気、水道などの公共料金の解約や名義変更
・携帯、インターネットの解約や名義変更
・年金関係の届出
・生命保険や医療保険の届出
早く遺品整理を行うべきケース
四十九日法要を待たずに、早く遺品整理を行ったほうがよいケースもあります。
次の3つのケースに当てはまるなら、早めに遺品整理を行いましょう。
・故人が賃貸物件や高齢者施設などに住んでいた場合
・相続放棄の可能性がある場合
・財産が非課税額を超えていた場合
亡くなられた方が賃貸物件に住んでいた場合、そのまま借り続けてはその期間も家賃が発生します。
家賃の負担を抑えるために、葬儀後すぐに遺品整理をしてもよいでしょう。
また、遺産に負債が多く相続放棄を検討している場合には、早めに遺品整理をする必要があります。
相続放棄には相続が発生したことを知った日から3ヶ月間という期限があり、それを超えてしまうと放棄できなくなるからです。(※1)
※1出典:裁判所「相続の放棄の申述」
財産が非課税額を超えていた場合は、申告書を作成して税務署に提出しないといけません。
申告書の提出期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と決められています。(※2)
※2出典:国税局「相続税の申告と納税」
遺品整理の流れ
遺品整理を行うにあたって、何から始めたらよいのかわからないと戸惑う方も多いでしょう。
スムーズに遺品整理を行えるように流れを紹介します。
1.貴重品を見つけて別の場所に保管する
遺品のなかには相続の手続きに必要な貴重品が含まれています。
他のものと一緒に処分することのないように、先に取り出して別の場所で大切に保管しておきましょう。
貴重品とは、具体的には次のものを指します。
・預貯金通帳
・有価証券(株式・小切手・債券など)
・印鑑
・年金手帳
・運転免許証やマイナンバーカード、保険証など
・不動産の権利書など
・金貨や高価な宝石など

2.残すものと処分するものに分ける
貴重品を保管したあとは、残すものと処分するものに分けましょう。
残すものとして挙げられるのは、思い出の品や価値のあるものなどです。
買取してもらえたり貰い手が見つかったりしそうなものは残します。
また、故人の愛用品などは、最終的に親族や近しい方などに贈る形見分けの品にもなります。
残すものとして一般的なのは以下の通りです。
・写真アルバム
・故人の愛用品や趣味のもの(腕時計・ゴルフセット・カメラ・メガネ・アクセサリーなど)
・比較的新しい家電
・骨董品や掛け軸など
・保存状態のよい本など
・そのほか買取してもらえたり貰い手が見つかったりしそうなもの
一方、処分するものは次の通りです。
・開封済み、もしくは賞味期限切れの食品
・使い古しの布団や衣類など
・引き取り手の見つからない家財道具
・古くて危険な電化製品

3.残しておくものは保管・形見分けをする
残しておくべきものが決まったら、遺産分割協議が終わるまでは、保管しておきましょう。
高価な貴金属などは遺産分割協議書作成における資産として協議内容に含まれます。
遺産分割協議が終わるまで勝手に持ち出さないようにしましょう。
その他の残すものは、誰に譲るかを考えます。
故人がエンディングノートを残している場合には、愛用品を誰に譲渡するかを記入されているかもしれません。
形見分けとして、親族や故人の友人など近しい方に譲ります。
また、価値はあるものの貰い手が見つからない品物は、買取業者やリサイクルショップなどに依頼して引き取ってもらいましょう。
4.不用品回収・自治体の収集などを利用して処分を行う
処分するものは自治体のルールに従って分別します。
主なゴミの種類は以下の通りですが、分別ルールは自治体によって異なります。
・可燃ゴミ
・不燃ゴミ
・資源ゴミ
・粗大ゴミ
また、遺品整理をしていくなかで処分するものが多い場合などは、有料でゴミ収集を依頼したり直接ゴミ処理センターに運んだりする必要があります。
お住いの自治体に確認してみましょう。
処分する際に注意が必要なのは、家電リサイクル法で決められている電化製品です。
冷蔵庫・テレビ・エアコン・洗濯機(乾燥機)の4つが家電リサイクルの対象となっています。(※3)
家電を購入した店舗に連絡して引き取ってもらうか、指定の回収業者に依頼しましょう。
また、大きな家具など、自分たちでは運び出せないものがある場合には、不用品回収業者に依頼することも検討します。
業者によって料金体系が異なるため、複数の業者に見積もりを依頼して決めましょう。
※3 出典:経済産業省「家電4品目の『正しい処分』早わかり」
遺品整理で失敗しないコツ
やみくもに遺品整理を始めても、思うように進まなかったり途中で挫折してしまったりします。
失敗しないためには、遺品整理のポイントを正しく理解した上で片付けを始めることが大切です。
遺品整理で失敗しないためのコツを解説します。
・片付けの計画を立てる
・相続人全員で遺品整理を行う
・遺言書やエンディングノートを確認する
・書類や貴重品から探す
・処分に悩むものは保留にする
・自力では大変だったら業者に依頼する
複数人で作業すると、誰がどこを片付けたかわからなくなり、作業効率が悪くなることがあります。
事前に「誰が」「どこを」「どのように」片付けるのか計画を立てておきましょう。
また、遺品整理は人手が多いほど早く終わるため、できるだけ親族を多く集めて、片付けていきましょう。
自己判断で整理して処理しまうと、他の相続人から不満が出てトラブルに発展することもあります。
故人の生前に作成した遺言書やエンディングノートがないかも確認しておきましょう。
必要なものと処分したいもの、財産分与についてなど、故人の遺志が書かれているかもしれません。
もしも遺言状やエンディングのノートなどが見あたらないときは、親族間で話し合って遺品の取り扱いを決めます。
遺品整理を行う際は書類や貴重品から探しましょう。
予期していなかった資産が出てくると相続に影響する可能性があるからです。
仕分けに悩んだときは一旦保留にして、効率よく作業を進めることを優先します。
部屋中が荷物であふれている、ゴミが多すぎて手が付けられないといった問題が発生したら、遺品整理業者を利用するのもおすすめです。
遺品整理を業者に依頼するメリット・デメリット
遺品整理は行う作業が多く、家族だけで行うにはかなりの労力が必要です。
近年遺品整理を業者に依頼する方が増えていますが、業者を頼るのに抵抗があるという方もいるでしょう。
遺品整理を業者に依頼するメリットとデメリットを挙げます。
業者に依頼するメリット
・プロに依頼することで遺品整理が短期間で済む
・遺品の仕分け・買取・回収・処分を一貫で行える
・紛失した遺品の捜索をしてもらえる
・遠方から遺品整理に赴く必要がない
遺品整理業者は遺品整理のプロです。
慣れていない遺族だけで行うよりも素早く確実に遺品整理することができます。
賃貸住宅の退去日などが決まっていて、迅速に遺品整理をしなければならないときなどは、業者の手を借りるとよいでしょう。
業者に依頼するメリットについては、以下の記事も参考にしてみてください。
ワンズライフを利用されたお客様の声を掲載しています。
【関連記事】遺品整理の事例紹介!お客様の声から分かる業者に任せるメリットとは
業者に依頼するデメリット
・家族で遺品整理を行うよりもお金がかかる
・遺品整理を業者に依頼することで罪悪感を抱く場合がある
・悪質な業者によって必要なものを勝手に捨てられたり買取されたりする可能性がある
遺品整理を業者に依頼すると、自分たちで行うよりもまとまった費用がかかるのは事実です。
しかし、遺品整理を自力で行う場合には、仕事を何日も休んだり、遠方から数日間滞在したりする必要があります。
交通費や滞在費などを考慮すると、業者に頼んだほうが安いということもあるため、自力で遺品整理をするときにかかる費用と比較してみるのもよいでしょう。
また、買取も同時に行う遺品整理業者に依頼すると、自分たちでは価値がないと判断したものでも買い取ってくれる可能性があります。
買取代金を差し引くと業者に支払う費用が安くなり、結果的にお得に遺品整理を行うことができる可能性もあるのです。
大切な故人の持ち物を家族で片付けられないことに罪悪感を抱いたり、悪質な業者に騙されるかもしれないと不安になったりする方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、適切に業者を選ぶことができれば遺品を丁寧に扱う業者に出会えます。
ぜひ次にご紹介する遺品整理業者の選び方を参考に、少しでも不安を解消してよりよい業者を選んでください。
遺品整理業者を選ぶポイント
遺品整理業者は全国に数多く存在します。
大切なご家族が生前使っていたものを扱うのですから、実績があって信頼できる会社に任せたいものです。
遺品整理業者を選ぶときに確認しておきたいポイントをご紹介します。
「遺品整理士」の資格を持ったスタッフが在籍している
遺品整理業者を選ぶ際は「遺品整理士」という資格を持ったスタッフが在籍しているか確認してみましょう。
遺品整理士とは、一般社団法人遺品整理士認定協会が発行する民間資格です。
遺品整理に関する正しい手順と専門知識を身につけ、試験に合格した人のみに与えられる遺品整理のプロフェッショナルともいえる資格です。
遺品整理を行うこと自体に特別な資格は必要ありませんが、遺品整理士が在籍しているということは「正しい知識を持って業務に取り組んでいる会社」と判断するひとつの目安になるでしょう。
「優良企業」の認定を受けているか
一般社団法人遺品整理士認定協会では、法律を守って業務を適切に行っている遺品整理業者を「優良企業」と認定しています。
2025年1月現在1637社が協会に登録しており、優良企業の一覧は協会のホームページから閲覧できます。(※4)
万が一登録されている企業に依頼してトラブルがあった場合、協会に連絡すれば対処してくれるため安心です。
※4 出典:一般社団法人遺品整理士認定協会「優良企業一覧」
求めているサービスを提供しているか
遺品整理業者といっても、会社によって提供しているサービスは異なります。
たとえば、不用品回収では処分しにくい仏壇がある場合には、閉眼供養などのサービスを提供している会社を選ぶと、別途お坊さんを手配する必要がありません。
また、遺品整理業者が不動産会社や司法書士などと提携している場合には、空き家の売却や相続など幅広く相談できる窓口となり得るのです。
一般的に遺品整理業者がどのようなサービスを提供しているのかを知らないという方のために、参考として遺品整理ワンズライフで提供している基本的なサービスをご紹介します。
<遺品整理ワンズライフの基本的なサービス内容>
・無料見積り
・貴重品と搬出品の仕分け
・積み込み
・養生作業
・原状回復作業
・室内や水回りの清掃
・合同供養
・回収品のリサイクル
※上記は基本料金に含まれるサービス
・買取り査定
電話・メールの対応が丁寧
遺品整理業者を選ぶ際は、スタッフの対応も重要なポイントです。
言葉遣いが丁寧なことはもちろん、依頼者の質問や疑問に対して丁寧に答えてくれるかどうかも確認しておく必要があります。
対応のよい会社は当日の作業でも、遺品の扱いが丁寧だったり仏壇に手を合わせてくれたりと、満足度の高いサービスを受けられる確率が高いでしょう。
故人の大切な遺品を扱う作業だからこそ、お客様への心遣いが行き届いた遺品整理業者を選ぶことが大切です。
遺品整理業に関する許可証を持っているか
遺品整理では不用品の処分や買い取りを依頼することもあります。
家具や家電等の買い取り、リサイクルを依頼する場合は、遺品整理業者が「古物商許可証」を所持しているか必ず確認しておきましょう。
遺品整理業者が必要な届け出をせずに無許可で業務を行うと、依頼者まで罰則の対象になったり高額な費用を請求されたりするかもしれません。
よい会社はホームページで許可証を公開していることが多いため、依頼前に一度チェックしておくことをおすすめします。
遺品整理業者を選ぶときに注意したいこと
総務省行政評価局の調査によると、近年遺品整理業者とのトラブルについての相談が消費者から多く寄せられています。(※5)
しかし、金銭面でのトラブルは契約前に少し気をつけるだけで防ぐことが可能です。
遺品整理業者を選ぶ際に、注意したいことをご紹介します。
実際に家や部屋を見て見積もりを出してもらう
遺品整理業者に見積もりを依頼する際には、実際に家に訪問して遺品の量や状態を確認してもらいましょう。
多くの遺品整理業者は無料で見積書の作成サービスを行っています。
見積書の作成方法は会社によって異なりますが、電話やメールでヒアリングしただけで料金を提示する業者には注意が必要です。
見積もりと実際の荷物の量に相違があった場合など、想定以上の料金を請求されることがあるからです。
見積もりに金額の内訳が書かれているか確認する
業者から提示された見積もりに金額の内訳が書かれていることを確認しましょう。
何にどのくらいの費用がかかるのかが明記されていない場合、見積もりの金額が妥当なのか高すぎるのかがわかりません。
見積もりで提示された金額の内訳も含め、納得したうえで契約しましょう。
相見積もりをする
遺品整理業者を選ぶときは、複数の業者に相見積もりをすることをおすすめします。
遺品整理を何度も業者に依頼した経験があって慣れているという方はほとんどいないでしょう。
このため、業者から提示された見積もりが高いのか安いのかよくわからないまま、契約をしてしまいがちです。
また、見積もりが安いからといってすぐに契約してしまうと、あとから追加料金を請求されることもあります。
法外な金額で契約をしないためにも、複数の業者に相見積もりをして相場を知っておきましょう。
遺品整理は信頼が第一です。
良質なスタッフや企業としての体制が整っている会社を選びたいものです。
見積もりが法外な金額は論外ですが、逆に安すぎる場合も注意が必要です。
担当者の対応をしっかり見極めましょう。
※5 出典:総務省「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」
遺品整理の料金相場は?
遺品整理では料金をめぐるトラブルが後を絶ちません。
高額な料金を請求されたり、追加料金を請求されたりといったトラブルに遭わないためにも、事前に遺品整理の料金の相場を把握しておきましょう。
一般的に遺品整理会社の料金は、部屋の間取りや広さによって決まります。
下の表は、遺品整理会社に作業を依頼したときの料金の目安です。
なお、遺品の量などによって価格は前後するため、下記の料金はあくまで「ひとつの目安」と考えておきましょう。
|
間取り |
料金の目安 |
|
1K |
35,000~80,000円 |
|
1DK |
55,000~120,000円 |
|
1LDK |
70,000~200,000円 |
|
2DK |
110,000~250,000円 |
|
2LDK |
140,000~300,000円 |
|
3DK |
170,000~400,000円 |
|
3LDK |
190,000~400,000円 |
|
4LDK |
250,000~600,000円 |
他にも作業人数、作業時間、不用品の回収品目によっても価格は変動するため、事前に見積もりを出してもらうことをおすすめします。
まとめ
遺品整理を行う時期や進め方、遺品整理を業者に依頼する際の注意点などを解説しました。
遺品整理を業者に任せるのに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。
大家族が一緒に暮らしていた昔の日本でしたら、家族が総出で行えば遺品整理もそこまで難しくありませんでした。
しかし、単身で生活する高齢者が増え、ゴミの分別が複雑になる昨今では、家族だけで遺品整理を行うのは大変なことです。
肉体的、精神的な負担を軽減するためにも、しっかりと業者を選んで遺品整理を依頼することをおすすめします。
遺品整理業者を検討する際は、複数の業者に見積もりを依頼し、料金の内訳などについて納得してから契約をしましょう。
ワンズライフは安心と信頼のサービスを提供します。
スタッフが丁寧に思い出の品を扱います。
見積もりは無料なのでぜひ一度お問い合わせください。
おすすめ記事
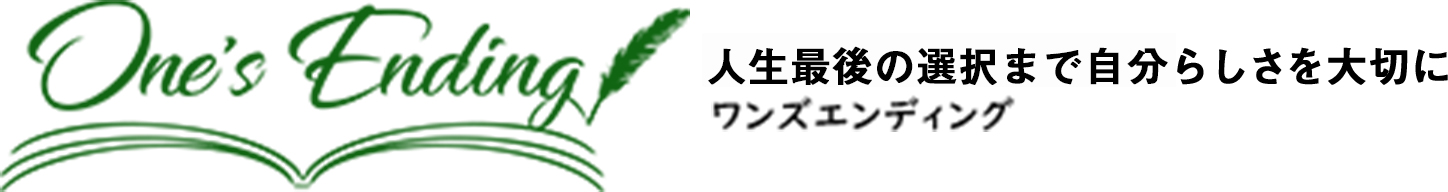




 " alt="グリーフケアの意味とは~身近な人を失った悲しみを乗り越える方法~">
" alt="グリーフケアの意味とは~身近な人を失った悲しみを乗り越える方法~"> " alt="遺品整理・生前整理の現場から~親の遺品整理ほどはかどらない">
" alt="遺品整理・生前整理の現場から~親の遺品整理ほどはかどらない"> " alt="遺品で買取してもらえるものとは?高く売るコツは?">
" alt="遺品で買取してもらえるものとは?高く売るコツは?"> " alt="賃貸物件が事故物件に?大家さんが知っておきたいクリーニング方法とは">
" alt="賃貸物件が事故物件に?大家さんが知っておきたいクリーニング方法とは"> " alt="遺品整理の業者を選ぶとき、依頼するとき、気を付けることまとめ">
" alt="遺品整理の業者を選ぶとき、依頼するとき、気を付けることまとめ"> " alt="遺品整理・生前整理の現場から~お客様の利益のためにできること">
" alt="遺品整理・生前整理の現場から~お客様の利益のためにできること">



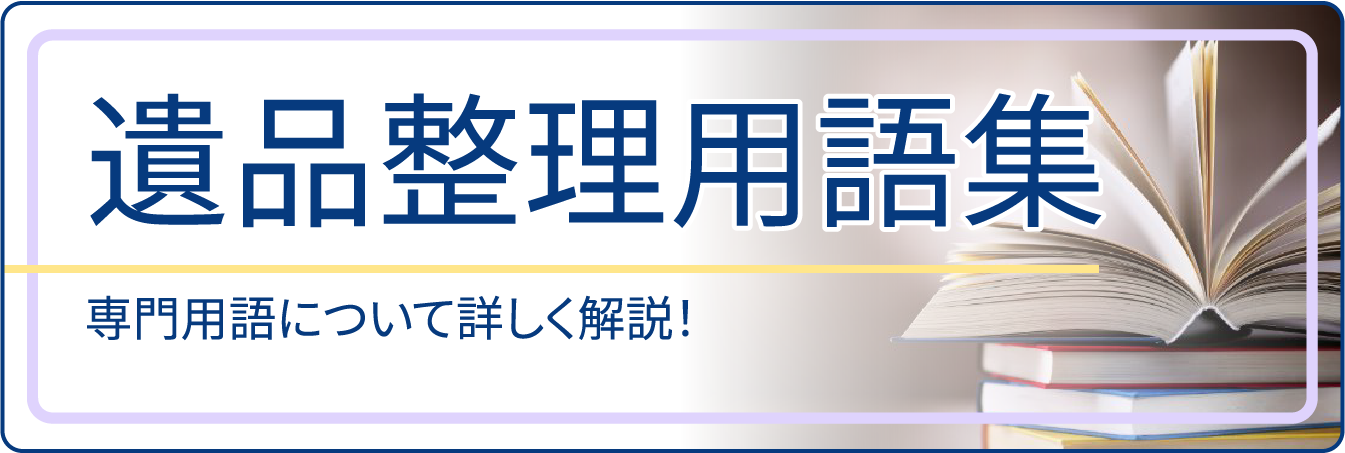





 " alt="賃貸物件で孤独死が発生した場合 原状回復の考え方と相続人の費用負担について">
" alt="賃貸物件で孤独死が発生した場合 原状回復の考え方と相続人の費用負担について"> " alt="形見分けとは~必ず行う?時期は?方法は?などの疑問を解決します~">
" alt="形見分けとは~必ず行う?時期は?方法は?などの疑問を解決します~"> " alt="遺品整理業者って、不用品回収や便利屋とどう違うの?">
" alt="遺品整理業者って、不用品回収や便利屋とどう違うの?">