
2020.10.19 (2025.06.27 One's Ending編集部 加筆)
生前整理でやることとは?リストを使った進め方のポイント
生前整理をしようと思っても「そもそも生前整理とはどこからどこまでのことを指すのだろう?」と戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
生前整理の範囲は人によってとらえ方がさまざまなため、中には「生きているうちに行うことすべてが生前整理なのでは?」と感じてしまい、「どこから手をつければいいのかわからない」と立ち止まってしまうケースもあります。
具体的に何をどうするかわからないまま整理を始めると、当初の予定通りに終わらなかったり、すべての作業が中途半端なまま挫折してしまったりするかもしれません。
本来の生前整理とは、ご自身が亡くなったあとに遺族が遺品整理や相続で困らないよう、財産関係や身分関係を整理しておくことです。
今回の記事では、生前整理でやることをリストにして、項目ごとに進め方のポイントをわかりやすくご紹介します。
また、生前整理を始めるタイミングや断捨離との違いについても解説しますので参考にしてみてください。
生前整理とは?断捨離との違いを知っておこう
はじめに「生前整理」と「断捨離」の違いを知り、ご自身がこれから行う作業がどちらに当てはまるのか考えてみましょう。
生前整理とは、ご自身が亡くなったあとに、遺族が遺品整理や相続で困らないよう、自分で財産関係を整理しておくことです。
一方、断捨離とは、ご自身が快適に暮らすために、不要なものを処分し、生活導線を確保することを指します。
以下に、断捨離がおすすめのケースと、生前整理がおすすめのケースを箇条書きでまとめました。
〈断捨離がおすすめのケース〉
・生活がしづらいので、物の量を減らしたい
・不用品を処分したい
・生活空間をシンプルにして、より快適に過ごしたい
→断捨離は「自分のための片付け」という意味合いが強い
〈生前整理を検討されるのがおすすめのケース〉
・認知症や物忘れが激しくなり、家族と同居することになった
・高齢者施設や福祉施設へ入居予定
・長期入院予定で自宅へ戻るかわからない
→生前整理とは「家族のための整理」という意味合いが強い
なお、遺品整理ワンズライフに生前整理のご依頼をいただくのは、認知症によってご自身で整理をすることが困難になった方や、介護施設などへの入居でご自宅を離れる予定の方が多数を占めています。
上記の〈生前整理を検討されるのがおすすめのケース〉に当てはまる場合は、これを機に生前整理を始めるのも良いかもしれません。
しかし、今後もその家に住み続ける予定で、生活を快適にするのが目的であれば、生前整理ではなく、まずは生活導線を確保する程度の断捨離を行うのが良いでしょう。
また、老人ホームや介護施設への引っ越しとなると、さまざまな準備や手続きが必要です。
「家を離れる予定だが、身辺整理といっても、何から始めれば良いかわからない」とお悩みの方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
【関連記事】介護施設・老人ホーム入居準備の注意点。引っ越しと生前整理のすすめ
生前整理を始めるタイミング
生前整理に「〇歳で始めるべき」といった、明確な決まりはありません。
自分の体力・体調・年齢・介護状況などを総合的に考えたうえで「そろそろ生前整理をした方がいいかもしれない」と思ったタイミングで始めるのが良いでしょう。
以下では、生前整理を始めるにあたって、遺品整理ワンズライフに片付けを依頼された方のケースをいくつかご紹介します。
①家族と同居するタイミングで
高齢になり、家族と同居するタイミングで生前整理を始められる方もいます。
2階建て以上の戸建てに住んでいて、寝室が上階にあると、毎日階段の昇り降りが必要です。
年を重ね、足腰が悪くなってくると、階段を昇り降りするのが難しくなり、1階のみで生活を送ることになります。
これまで暮らしてきた家での生活が難しくなり、家族と同居することになった場合は、荷物の整理を兼ねて生前整理を始めるのも良いでしょう。
②老人ホーム・施設へ引っ越すタイミングで
施設の種類によっては持っていける家具や家電の量が決まっています。
再び家に戻ってくる可能性が低い場合は、引っ越しのタイミングで財産や家財道具を整理しておいた方が良いでしょう。
短期入所で在宅での生活を目指す場合は、すべての家財道具を処分する必要はありませんが、ある程度片づけておくと戻ってきたときに生活しやすくなります。
③長期入院するタイミングで
病気やケガで長期入院する場合も、生前整理について考えるタイミングです。
快復して以前のように生活できればよいですが、年齢や病気・ケガの具合によっては、そのまま施設へ入居することになるかもしれません。
病院に入院して、治療を受けながら荷物や財産の整理を進めるのは大変です。
長期間家を離れることがわかっているときは、この機会に生前整理を考えてみるのもよいでしょう。
④自分で整理整頓をするのが難しくなったタイミングで
「どこに何があるかわからない」「物忘れが激しくなってきた」など、自分で整理整頓するのが難しくなったときも、生前整理を考えるひとつのタイミングです。
そのままでいると、家がゴミ屋敷になってしまい、いざ生前整理を始めようと思っても物が多すぎて、手が付けられなくなるかもしれません。
「以前は片付けられたのに、高齢になってから片付けられなくなった」という人の場合、認知症やうつ、統合失調症など、脳の病気や精神疾患の影響を受けている可能性も考えられます。
自分自身ではどうしても気づきにくいため、子どもや周囲の人から「片付けた方がいいよ」「生活に支障が出ているよ」などの指摘を受けたら、早めに家族に助けてもらったり、行政やプロの整理専門会社に相談したりすることが大切です。
生前整理を行うメリット
ご自身が亡くなると、家族は葬儀やお墓の準備のほか、遺品整理も行います。
誰が遺品整理するかについて決まりはありませんが、整理の専門会社に依頼しない場合は、子どもや親族が行います。
賃貸物件や売却予定の家であれば、退去期限までに整理を終わらせないといけません。
しかし、遺品の中には、通帳やキャッシュカード、保険関係の書類などの貴重品も含まれていますので、大切な物まで処分しないように細心の注意が必要です。
大切な家族が亡くなった悲しみの中、限られた時間の中で多くの荷物を分類し、遺品整理を進めるのは大変な手間と精神的負担がかかります。
あらかじめ生前整理をしておけば、遺品整理の際に子どもや家族への負担を軽減できるのです。
【関連記事】遺品整理と生前整理の違いと必要性を解説
また、財産関係を整理して遺産分割について決めておけば、自分が亡き後に家族間で相続に関するトラブルを回避できるかもしれません。
身の回りの財産を整理しておくことで、現在の資産の状態が把握しやすくなり、今後のマネープランも立てやすくなるでしょう。
【関連記事】生前整理とは?必要性はある?進め方を徹底解説

生前整理でやることリスト&進め方のポイント
いきなり生前整理に取り掛かろうとすると「あっちの片付けを忘れていた」「終わったと思っていたら、後で片付けていないものが出てきた」などの作業漏れが発生し、整理がスムーズに進みません。
そういったトラブルを防ぐためには、あらかじめやるべきことを“リスト化”し、ひとつひとつの項目を確認しながら作業を進めていくことが大切です。
以下に「生前整理でやることリスト」を作成しました。
〈生前整理でやることリスト〉
|
① |
財産目録を作る |
|
② |
物を仕分けて「必要な物」と「不要な物」を決める |
|
③ |
不用品の処分を行う |
|
④ |
不動産の整理を行う |
|
⑤ |
デジタル整理をする |
|
⑥ |
エンディングノートを書く |
次に、それぞれの項目の詳細な内容と、進め方のポイントを見ていきましょう。
なお、今回は先ほどご説明した認知症や介護施設などへの引っ越しをきっかけに空き家となった実家を片付ける「生前整理」だけでなく、生活導線を確保するための「断捨離」も含めて話を進めていきます。
①:財産目録を作る
まずは、家族に残す財産の目録を作成します。
「目録」とは、所有している物の品目や内容をわかりやすく一覧にしたリストのことです。
生前整理の際に財産目録を作成しておけば、家族はどんな相続財産があるのかすぐにわかります。
財産目録に書き記しておきたい内容は、以下の通りです。
〈財産目録の内容〉
・健康保険、年金手帳、生命保険、医療保険の加入歴がわかる書類
・各種保険証券
・土地や不動産関係の権利書
・預金通帳
・現金(自宅の金庫などで保管している場合)
・有価証券
・絵画や壺などの骨董品・美術品
・宝石や貴金属
・車などの資産価値が高いもの
・住宅ローンや借入金の残高
進め方のポイント
目録には、財産の内容だけでなく、わかる限りで金額や評価額を合わせて記入しておきます。
また、財産の保管場所も目録に書いておけば、家族がひとつひとつ探す手間も省けます。
もし住宅ローンや借入金などがある場合は、負債額についてもできるだけ具体的に記しておきましょう。
遺産相続のときに、財産よりも負債額の方が多いと家族は損をしてしまいます。
財産目録があれば、家族が相続前に財産の総額を確認し、負債額の方が多ければ対策として相続放棄をすることも可能です。
②:物を仕分けて「必要な物」と「不要な物」を決める
次に、家の中にあるものを「必要な物」と「処分する物」に仕分けしていきます。
処分するか判断に悩むものは「保留」にして、あとでじっくり必要な物か考えるのがよいでしょう。以下に、不用品として選定しておきたい物の一例をまとめました。
〈不用品として処分する物の一例〉
・もう着る予定がない服、何十年も使用していない雑貨類
・使用不可能な家具や家電
・ゴルフセットやバット、グローブや釣り竿などの趣味の物(もう使用しない場合)
・古本、古雑誌
・アルバムや写真
進め方のポイント
長年住んでいた家には、思ったより多くの物があるため、ひとつひとつを仕分けていくとかなりの時間がかかります。
処分に悩むたびに手を止めてしまうとなかなか作業が進まず、計画通りに整理が終わらないことでやる気をなくしてしまったり、途中で挫折してしまったりするかもしれません。
迷ったときは「保留」にして、できるだけ手早く仕分けを進めましょう。
一通り物を分類できたら、もう一度「保留」にある物を確認して「やっぱり不要なもの」か「置いておきたい物」なのか考えます。
「置いておきたい物」に分類されたものは段ボールや箱にまとめ、置き場所を決めて保管しておきましょう。
そして、1ヶ月や3ヶ月など、定期的に中身を見直す方法がおすすめです。
③:不用品の処分を行う
仕分けが終わったら「処分する物」をさらに「売る物」と「捨てる物」の2種類に分けていきます。
中には「こんな物売れるの?」と思う物もあるかもしれませんが、何十年も前の物であっても欲しい人がいる場合はそれなりの価格がつくことがあり、買い取ってもらえる可能性もゼロではありません。
売却することでお小遣いになるかもしれませんので、捨てる前に一度査定に出してみることをおすすめします。
売りたい物の量が多くてリサイクルショップに持って行くのが難しいときは、宅配買取サービスを活用するのも良いでしょう。
また、最近では「メルカリ」や「ラクマ」など、フリマアプリを使用して不用品を出品する方も増えています。
「捨てる物」に分類されたものは、お住まいの自治体のルールに従い、正しい方法で処分しましょう。
生前整理で出た不用品の処分方法については、以下のコラムで詳しく解説しています。捨て方に迷った際はご参照ください。
【関連記事】遺品整理、生前整理で出た不用品の処分方法まとめ
進め方のポイント
売りたいものは「いつか売るから置いておこう」とそのままにせず、期間を決め、早めに手放しましょう。
物を置いておくにはスペースを確保する必要があるため、いつまでたっても整理が終わらなくなります。
フリマアプリで出品するときは「1週間以内に売れなかったら捨てる」、誰かに譲ろうと考えているなら「1ヶ月以内に欲しい人がいなかったら処分する」など、保管期間をきちんと決めておくことがポイントです。
④:不動産の整理を行う
相続財産に不動産が含まれる場合は、事前にしっかりと整理しておきましょう。
不動産はトラブルが起きやすく、相続に思ったよりも手間がかかることがあります。
また、アパートやマンションを保有して大家となっていれば、後で立ち退き問題なども発生するかもしれません。
ご自身が健康であったり、その家に長く住む予定であったりすればすぐに不動産を整理する必要はないかもしれませんが、万が一に備えて相続方法を知っておけば、手続きの際に落ち着いて対処できます。
不動産の相続の方法について簡単にご紹介します。
〈不動産の相続の方法〉
① 現物分割……不動産をそのままの形で相続する方法。
ひとつの土地を分割して相続人がそれぞれ単独取得する場合や、複数の不動産を相続人が単独で取得する場合などがある。
② 換価分割……不動産を売却して、現金化して相続する方法。
③ 代償分割……相続人の中の1人がすべての不動産を相続し、ほかの相続人にはそれに見合う現金を渡す方法。
相続遺産が1億円で相続人が5人いる場合は、すべての不動産を引き継ぐ人が、ほかの相続人4人に2,000万円ずつ支払う。
④ 共有分割……不動産を複数の相続人で共有する方法。現物分割と違って、分割の協議は不要となる。
進め方のポイント
これらの4つの分割方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。
生前整理の一環で不動産の相続を行う場合は、ご家族としっかり話し合い、1番納得できる方法を模索することが大切です。
いくら相続トラブルを回避するためとはいえ、思い入れがある不動産を生前に手放すのは、なかなか勇気のいることです。
ご自身が健康で、まだ決心がつかないときは、焦って売却する必要はないでしょう。
⑤:デジタル整理をする
「デジタル遺品」とは、パソコンやスマートフォンのデータ、SNSのIDやパスワード、ネット銀行の口座、仮装通貨FXの情報などです。
デジタル情報は、セキュリティが高い反面、本人以外の人が操作するのは難しいというデメリットがあります。
いざというときに家族の方が困らないよう、事前にパスワードやID、設定などを確認しておきましょう。
以下に、デジタル遺品の整理方法についてまとめました。
〈デジタル遺品の整理方法〉
① パソコンやスマートフォン……不要なメールは事前に削除しておき、残しておきたい大切なメールに目印をつけておく。
写真や動画も同様に、残さないものがあれば削除しておく。
ロックをかけている場合は、エンディングノートなど、普段家族が目につかない場所にパスワードを書き記しておく。
② SNSアカウント……アカウント名、ID、パスワードを書き記しておく。何年も稼働していない不要なアカウントは削除しておく。
③ ネット銀行の口座や仮装通貨、FX情報など……銀行名、ID、パスワードを記しておくとともに、年会費の有無についても記載。第二パスワードや、個人情報変更の際に必要な「秘密の質問」なども設定していれば、合わせて記載しておく。
デジタル遺品の整理方法については、以下のコラムでさらに詳しく解説しています。
デジタル遺品にまつわるトラブル事例やエピソードもご紹介していますので、合わせてご参照ください。
【関連記事】デジタル遺品とは?パソコンやスマホに残るデータの遺品整理・生前整理
進め方のポイント
デジタル遺品の整理を進めるときは、IDやパスワードだけでなく、登録しているサイトのURLをブックマークしたり、パソコンのデスクトップ画面にアイコンで残しておいたりして、家族が見たときに一目でわかるようにしておきましょう。
ご自身は毎日触っているのでどこに何の情報があるか把握できていても、家族がまったくわからないと、整理に手間取ってしまいます。
パソコンの場合は「解約してほしいネット銀行」など、フォルダを作成しておくのもおすすめです。
⑥:エンディングノートを書く
財産目録、自分にもしものことがあったときに知らせて欲しい友人・知人の連絡先、介護・葬儀についての希望、さきほどご紹介したデジタル遺品の情報などは、エンディングノートを作成することで1冊にまとめることができます。
エンディングノートは、過去の振り返り、これからの目標、死後の希望など、人生や自分に関するあらゆる内容を書き記せるノートです。
終活の一環として、近年急速に認知度が高まりました。
遺言書と違って法的効力はなく、様式も決まっていませんので、本屋やインターネットで販売されているものを購入しても、自作しても構いません。
以下に、エンディングノートに書き記しておきたい内容の一例をまとめました。
〈エンディングノートに記入しておく内容の一例〉
・ご自身の基本情報(生年月日や本籍地、家系図など)
・財産の情報
・医療や老後の介護の希望
・友人、知人の連絡先
・葬儀やお墓の希望
・デジタル遺品の情報
・家族や親族、周囲の方へのメッセージ
・ペットのこと
エンディングノートのメリット・書き方・選び方などについては、ワンズエンディングのこちらのコラムでわかりやすく解説していますので、合わせてご参照ください。
【関連記事】エンディングノートとは何?メリットやオススメの選び方と書き方を解説
進め方のポイント
エンディングノートは一度書いたら終わりではありません。
何年かすれば、ご自身の気持ちやお金のこと、健康状態など、身の回りの状況は変わっている可能性もあります。
1年に1回など、期間を決めて、定期的に見直しをしましょう。
まとめ~自分や家族で行うのが大変なら業者に頼むのもひとつの案~
生前整理はやることが多く、かなりの時間を要する作業です。
私たちの生きている時間には限りがありますので、何かに時間を使えば、その分ほかのことをする時間が減ってしまいます。
生前整理を自分たちで行うと数か月かかってしまうという場合は、プロの業者に依頼するのもひとつの手です。
業者なら自分で作業するよりも早く終わるので、その分の時間をより有益に使えます。
また、ご自身がご高齢であれば、腰をかがめる作業や荷物の運び出しは体に負担がかかり、1人で整理を行うのが難しい場合もあるでしょう。
生前整理は子どもや親族に任せることもできますが「自分の荷物を勝手に捨てられるかもしれない」「見られたくないものがある」など、肉親だからこそ生前整理を任せにくいご事情もあります。
このように、作業量が多くて時間がかかってしまう場合や、ご自身で進めるのが困難だと感じた場合は、生前整理を代行してくれる業者への依頼・相談を検討されてみてはいかがでしょうか。
ただ、全国に生前整理を行う会社は数多く存在し、サービス内容や企業の方針はそれぞれ異なります。
生前整理を業者に依頼するなら、プロとしての高い意識を持ち、依頼者の気持ちを第一に考えて作業に取り組んでくれる会社を選ぶことが重要です。
ワンズライフでは生前整理にも対応しています。
豊富な経験を持つスタッフが、全力でサポートいたします。
生前整理でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
おすすめ記事
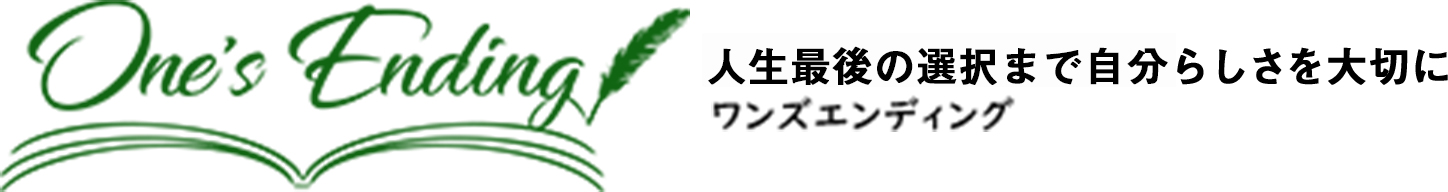




 " alt="遺品整理・生前整理の現場から~原状回復はどこまで?">
" alt="遺品整理・生前整理の現場から~原状回復はどこまで?"> " alt="40代・50代でやるべき老前整理とは?メリットと成功のコツ">
" alt="40代・50代でやるべき老前整理とは?メリットと成功のコツ"> " alt="親の家を片付けるときに気を付けたい、OKワードとNGワード">
" alt="親の家を片付けるときに気を付けたい、OKワードとNGワード"> " alt="リバースモーゲージ制度の概要とメリット・デメリット">
" alt="リバースモーゲージ制度の概要とメリット・デメリット"> " alt="遺品整理・生前整理の現場から~遺品査定士による買取">
" alt="遺品整理・生前整理の現場から~遺品査定士による買取"> " alt="遺品整理と生前整理の違いと必要性を解説">
" alt="遺品整理と生前整理の違いと必要性を解説">



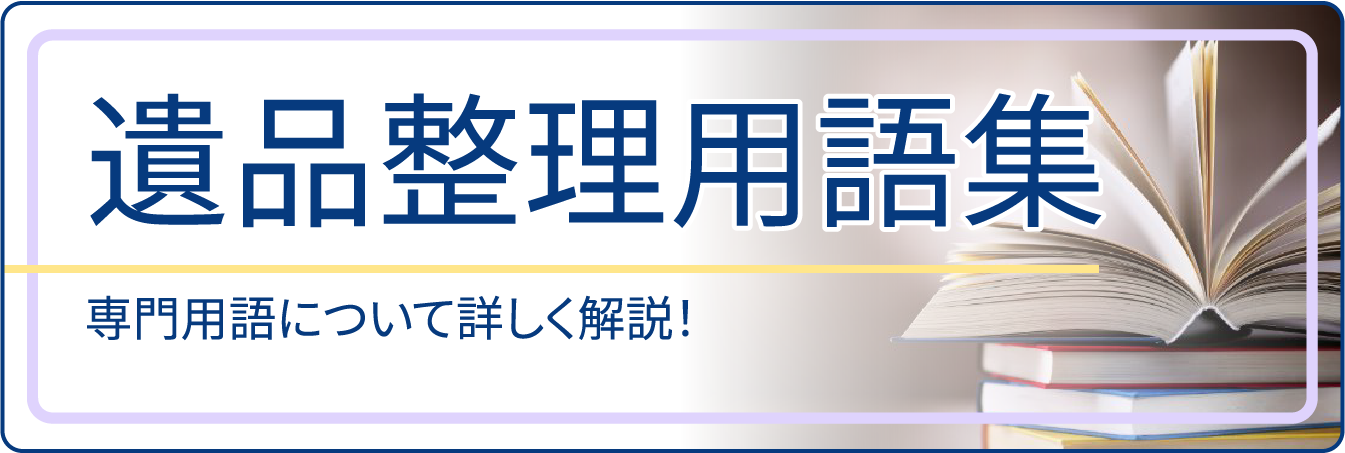





 " alt="実家の片付けが進まない!片付ける順番と成功のコツ">
" alt="実家の片付けが進まない!片付ける順番と成功のコツ"> " alt="断捨離の意味と効果とは?実践体験談から分かるメリット・デメリット">
" alt="断捨離の意味と効果とは?実践体験談から分かるメリット・デメリット">